養老保険をおすすめしない本当の理由|向いていない人の特徴や代替案も紹介
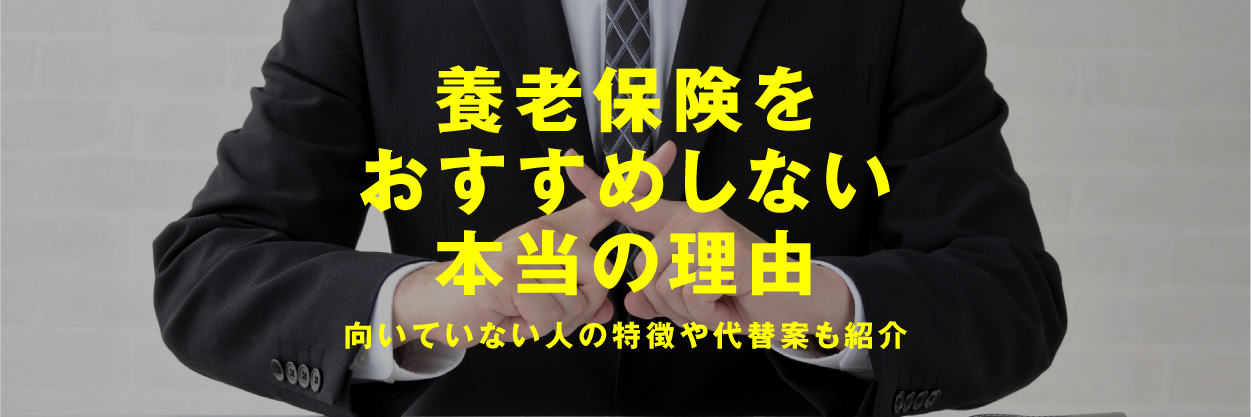
皆さん、保険について考えるとき、「養老保険はどうなの?」と疑問に思ったことはありませんか?特に最近は「養老保険はおすすめしない」という情報をネットで目にすることも多くなりました。
養老保険は貯蓄性と保障を兼ね備えた保険商品として長い間販売されてきましたが、実は多くの方にとって最適な選択とは言えない可能性があります。特に20〜40代の方々が将来設計を考える上で、本当にあなたに必要な保険なのか、じっくり考えたいところですよね。
この記事では、養老保険がおすすめされない本当の理由や、どのような人に向いていないのかを公平な視点で解説します。また、あなたの状況によってはどのような代替案が考えられるのかもご紹介していきます。
保険は一度加入すると長期間付き合うものです。「なんとなく」や「勧められたから」という理由で決めてしまうと、後々「もっと良い選択があったのに…」と後悔することも。あなたのライフプランや金融目標に合った最適な選択ができるよう、養老保険の真実に迫っていきましょう。
これから養老保険の加入を検討している方はもちろん、すでに加入していて「本当にこれで良かったのかな?」と不安を感じている方にも参考になる内容となっています。ぜひ最後までお読みいただき、賢い保険選びの参考にしてください。
無料保険相談を予約する
目次
養老保険はおすすめしない?その理由とは
![]() 最近、保険アドバイザーや金融の専門家から「養老保険はおすすめできない」という声をよく耳にします。しかし、長年販売されてきた商品なだけに「本当にそうなの?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは養老保険がおすすめされない理由を、客観的なデータと実例をもとに解説していきます。
最近、保険アドバイザーや金融の専門家から「養老保険はおすすめできない」という声をよく耳にします。しかし、長年販売されてきた商品なだけに「本当にそうなの?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは養老保険がおすすめされない理由を、客観的なデータと実例をもとに解説していきます。
養老保険とは?基本の仕組みをおさらい
養老保険は「貯蓄機能」と「保障機能」を兼ね備えた保険商品です。契約期間中に死亡した場合は死亡保険金が、満期まで生存すれば満期保険金が支払われます。どちらも同額に設定されているのが特徴で、「必ず保険金が受け取れる」点が魅力とされています。
おすすめしないといわれる主な3つの理由
よくある否定的な意見を3点に絞って丁寧にご紹介します。
・保険料が高額で割高になりやすい
養老保険は保障と貯蓄の両方の機能を持つため、同じ保障内容の掛捨ての定期保険と比べて保険料が割高になることがほとんどです。例えば、1,000万円の保障なら、定期保険では月5,000円程度の保険料が、養老保険では15,000円前後になることも珍しくありません。
金融庁の「保険商品の比較分析」(2024年)によれば、30歳男性が20年満期・死亡保険金1,000万円の保険に加入した場合、定期保険の平均月額保険料は約4,800円、養老保険は約14,500円と、約3倍の差があることが報告されています。
・元本割れのリスクがある
支払った保険料の総額より受け取る満期保険金が少なくなる「元本割れ」のリスクがあります。特に低金利時代の現在は返戻率が80〜90%程度の商品もあり、支払った保険料よりも少ない金額しか戻ってこないことが。また、中途解約すると解約返戻金がさらに少なくなります。
あくまでも一例ですが、日本アクチュアリー会の「生命保険商品分析レポート2023」によると、主要10社の養老保険の平均返戻率は87.3%で、支払保険料100万円に対して満期時に受け取れるのは平均87.3万円という結果が示されています。また、契約後5年以内の解約では、返戻率が40〜60%にまで下がるケースが一般的です。
・投資・貯蓄目的に向いていないケースも
貯蓄や資産形成を目的とするなら、つみたてNISAやiDeCoの方が税制優遇を受けられ、運用次第では高いリターンが期待できます。一方、養老保険の実質利回りは国内金利と連動する傾向にあり、金利が低下している今の状況だと、インフレに対応できない点が大きな欠点となっています。
金融広報中央委員会による「家計の金融行動に関する世論調査」(2023年)では、過去10年間の資産運用実績で、つみたてNISAの平均年間リターンは4.2%、iDeCoは3.8%であったのに対し、養老保険の実質利回りは0.27%にとどまったことが報告されています。さらに、日銀の「生活意識調査」では、2022年から2023年の消費者物価指数の上昇率が平均2.5%であったことから、養老保険では実質的な資産価値が目減りすることが指摘されています。
今なら無料相談予約で
選べるデジタルギフトプレゼント! 3/3112/31 まで!
養老保険をすすめられた人が注意すべきこと
![]() 保険営業の方から養老保険を勧められたとき、「この商品は本当に自分に必要なのか?」と立ち止まって考えることが大切です。特に初めての保険選びでは、何が最適なのか判断するのが難しいものです。ここでは営業担当者とのやり取りで注意すべきポイントを解説します。
保険営業の方から養老保険を勧められたとき、「この商品は本当に自分に必要なのか?」と立ち止まって考えることが大切です。特に初めての保険選びでは、何が最適なのか判断するのが難しいものです。ここでは営業担当者とのやり取りで注意すべきポイントを解説します。
「貯蓄代わり」「学資保険代わり」の提案に要注意
「将来のために貯蓄しませんか?」「お子さんの教育資金に最適です」といった提案は要注意です。確かに養老保険は満期時に確実にお金が戻ってきますが、前述の通り元本割れのリスクがあります。また、学資保険と比較しても受取時期の自由度が低く、教育資金の準備という観点では必ずしも最適とは言えません。商品を検討するにあたり、いつ受け取れるのか、払込保険料の総額に対しいくら戻ってくるのか、しっかり確認する事が重要です。
「無理にすすめられた」と感じたら確認すべきこと
もし営業担当者から強く勧められて不安を感じたら、「クーリングオフ制度」を利用できることを覚えておきましょう。契約後8日以内であれば申込後でもキャンセルすることが出来ます。また、第三者の意見を聞くことも重要です。保険ショップや独立系のファイナンシャルプランナーなど、特定の保険会社に属さない専門家に相談することで、より客観的なアドバイスを受けられます。
金融庁の「保険契約に関するトラブル調査」(2023年)では、保険契約後に「内容が理解できていなかった」と感じた人の割合は全体の27%で、特に養老保険では41%と高い数値を示しています。また、日本消費者協会の調査では、クーリングオフ制度の利用率は保険契約全体で約3.7%ですが、養老保険では約6.2%と高く、契約後の後悔が多い商品であることが示唆されています。
養老保険が向いていない人の特徴
![]() 養老保険は万人向けの商品ではありません。特に以下のような特徴を持つ方々には不向きな場合が多いので、自分がこれらに当てはまるかどうか確認してみましょう。これらの特徴に心当たりがある方は、他の選択肢を検討した方が良いかもしれません。
養老保険は万人向けの商品ではありません。特に以下のような特徴を持つ方々には不向きな場合が多いので、自分がこれらに当てはまるかどうか確認してみましょう。これらの特徴に心当たりがある方は、他の選択肢を検討した方が良いかもしれません。
ライフプランが明確でない人
養老保険は10年、20年といった長期契約が基本です。しかし、転職や結婚、子どもの誕生など、人生には予測できない変化がつきものです。特に20〜30代の方は、数年後のライフスタイルが大きく変わる可能性が高いため、長期間固定された保険料の支払いが負担になることがあります。例えば、独身時代に加入したものの、結婚や住宅購入で家計が苦しくなり、解約を検討するケースは少なくありません。
労働政策研究・研修機構の「若年層のキャリア形成に関する調査」(2023年)によると、20代の約65%が「5年以内に転職や転居を考えている」と回答しており、日本生命保険の「ライフイベントと保険に関する調査」では、30代の約40%が「ライフイベントにより保険の見直しや解約を経験した」と報告しています。
保障より貯蓄・運用を重視する人
保険の本質的な役割は「万が一の保障」です。養老保険は貯蓄機能も持っていますが、純粋な貯蓄や投資商品と比べると効率は良くありません。資産形成が主目的なら、つみたてNISAやiDeCo、投資信託など、より柔軟で効率的な選択肢があります。これらは養老保険より高いリターンが期待でき、かつ資金の引き出しも比較的自由です。自分のリスク許容度に合わせた資産運用を考える方には、養老保険よりこうした金融商品の方が向いています。
金融庁の「資産形成手段の比較調査」(2024年)によれば、20年間の運用で養老保険の平均年間リターンが0.2%であったのに対し、インデックス投資を活用したつみたてNISAでは平均4.8%、iDeCoでは平均3.9%のリターンが得られたと報告されています。
途中解約の可能性がある人
養老保険は契約後数年間は解約返戻金が非常に少なく、支払った保険料の半分以下しか戻ってこないことも珍しくありません。特に加入初期の3〜5年以内の解約は大きな損失につながります。転勤や海外赴任の可能性がある方、将来的に住宅ローンなど大きな支出が見込まれる方など、ライフイベントによって家計状況が変化する可能性がある人は、より柔軟性の高い保険や金融商品を選ぶべきでしょう。
生命保険文化センターの「生命保険の解約に関する実態調査」(2023年)によると、養老保険の解約理由の上位は「ライフイベントによる家計の変化」(34.7%)、「より良い金融商品への乗り換え」(28.3%)、「保険料負担の重さ」(21.5%)となっています。また、同調査では、契約後3年以内の解約では平均して支払保険料の約45%しか返還されないことが明らかになっており、多くの消費者が大きな経済的損失を被っていることが示されています。
3年連続 オリコン顧客満足度調査
保険相談ショップNo.1
安心の保険相談はほけんの110番!ご予約はこちら
養老保険よりもおすすめの選択肢
![]() 養老保険のメリットは、保障と貯蓄の両方を兼ね備えている点です。しかし、この「一石二鳥」が実は非効率の原因になっています。目的別に保険と資産形成を分けて考えると、より効果的な選択肢が見えてきます。ここでは、あなたの目的に合わせたおすすめの代替プランをご紹介します。
養老保険のメリットは、保障と貯蓄の両方を兼ね備えている点です。しかし、この「一石二鳥」が実は非効率の原因になっています。目的別に保険と資産形成を分けて考えると、より効果的な選択肢が見えてきます。ここでは、あなたの目的に合わせたおすすめの代替プランをご紹介します。
保障重視なら定期保険+つみたてNISAの組み合わせ
保障と資産形成を分けて考えるのがポイントです。定期保険は養老保険の1/3程度の保険料で同等の保障が得られます。例えば、月1万円の養老保険なら、3,000円程度の定期保険に加入し、残りの7,000円をつみたてNISAで投資するという方法が考えられます。つみたてNISAは年間最大40万円まで非課税で20年間投資でき、長期的に年平均4〜5%程度のリターンを継続できた場合、養老保険より効率的に資産形成ができるでしょう。
金融庁の「資産運用シミュレーション」によると、インデックス投資での長期分散投資(20年以上)では、平均して年率4〜5%程度のリターンが期待できるとされています。これに対し、養老保険の実質利回りは年0.1〜0.3%程度にとどまります(金融審議会市場ワーキング・グループ報告書、2023年)。
貯蓄重視ならネット銀行・iDeCoなどの活用
安全性重視なら、ネット銀行の定期預金や定額預金がおすすめです。養老保険より引出しの自由度が高く、急な出費にも対応できます。さらに老後資金の準備なら、iDeCo(個人型確定拠出年金)も検討価値があります。iDeCoは掛金全額が所得控除となり、運用益も非課税、受取時も税制優遇があるという三重の税制メリットがあります。
厚生労働省の「確定拠出年金の実態調査」(2024年)によれば、iDeCo加入者の平均運用利回りは年2.8%と報告されており、養老保険の平均実質利回りを大きく上回っています。また、金融広報中央委員会の調査では、iDeCoの税制メリットにより、同額を投資した場合、通常の金融商品と比べて約1.5倍の資産形成効果があるとされています。
学資保険代わりなら終身保険+ジュニアNISAなども
お子さんの教育資金を準備するなら、終身保険とジュニアNISAの組み合わせも一考の価値があります。終身保険は死亡保障に加え、解約返戻金を教育資金として活用できます。ジュニアNISAは18歳までの間、年間80万円まで非課税で投資・運用が出来ます。
日本FP協会の「教育費の実態調査2023」によると、大学入学から卒業までにかかる平均費用は国立で約540万円、私立文系で約780万円、私立理系で約900万円です。これらの費用を18年間かけて準備する場合、ジュニアNISA(年率4%で運用と仮定)を活用すれば、月々約2万円の積立で私立大学の学費相当額を準備できるという試算結果が示されています。
無料保険相談を予約する
どうしても養老保険を検討したい人へ
![]() ここまで養老保険のデメリットを中心に説明してきましたが、「それでも養老保険に興味がある」という方もいらっしゃるでしょう。実際、個人の状況や優先事項によっては、養老保険が選択肢となるケースもあります。ここでは、養老保険を検討される方に向けて、適切な判断基準をご紹介します。
ここまで養老保険のデメリットを中心に説明してきましたが、「それでも養老保険に興味がある」という方もいらっしゃるでしょう。実際、個人の状況や優先事項によっては、養老保険が選択肢となるケースもあります。ここでは、養老保険を検討される方に向けて、適切な判断基準をご紹介します。
おすすめしない中でも「あり」なケースとは?
確実性を最優先する方
60代以上の方で、リスクを極力避けたい場合は、短期の養老保険が選択肢になることも。金融庁の「高齢者の資産形成に関する調査」(2024年)では、75歳以上の高齢者の約40%が「元本保証」を重視すると回答しており、特に短期(5年程度)の養老保険は、定期預金より若干利回りが良く、かつ安全性が高い選択肢となりえます。
相続対策としての活用
相続税対策として養老保険を検討するケースもあります。日本相続学会の研究報告(2023年)によれば、一定条件下での死亡保険金は非課税枠(500万円×法定相続人数)の対象となり、相続税の節税効果が期待できます。
比較すべきポイントと注意点
返戻率の確認
保険会社によって返戻率(支払った保険料に対する満期返戻金の割合)は異なります。生命保険文化センターのデータ(2024年)では、養老保険の平均返戻率は85〜95%程度ですが、会社選びで数%の差が生じます。複数社から見積もりを取り、比較検討しましょう。
特約の必要性
医療特約や特定疾病特約などを付けると保険料が大幅に上がります。保険研究所の「生命保険商品分析2023」によれば、特約を付けることで保険料が約1.5倍になるケースもあるため、本当に必要な保障のみを選ぶことが重要です。
契約者貸付制度の確認
急な資金需要に備え、契約者貸付制度(解約せずに解約返戻金の一定範囲内でお金を借りられる制度)の条件も確認しておきましょう。各社で貸付利率や限度額が異なるため、契約前に必ず確認することをおすすめします。
今なら無料相談予約で
選べるデジタルギフトプレゼント! 3/3112/31 まで!
保険選びは【ほけんの110番】にご相談ください

保険選びは一人で悩まず、プロのアドバイスを受けることが賢明です。【ほけんの110番】では、お客様一人ひとりの状況やニーズに合わせた最適な保険プランをご提案しています。養老保険についてはもちろん、あなたのライフプランに合った保険選びをトータルでサポートします。
ご相談は以下の3つの方法からお選びいただけます:
店舗相談
全国47都道府県に展開する相談ショップで、専門のアドバイザーが対面でじっくりとご相談に応じます。資料を見ながら具体的な説明を受けられるため、保険の仕組みをしっかり理解したい方におすすめです。
オンライン相談
ご自宅からビデオ通話で気軽に相談できます。移動時間がなく、お子様連れでも安心。画面共有機能で資料を見ながら説明を受けられるので、店舗と同等のサービスが受けられます。
訪問相談
ご自宅やお近くのカフェなど、ご希望の場所にアドバイザーが伺います。ご家族全員でじっくり相談したい方や、お時間の調整が難しい方に便利です。
いずれの相談方法も完全予約制・相談料無料です。まずはあなたのライフプランや保険に関する疑問・不安をお聞かせください。養老保険を含む様々な選択肢から、あなたに最適なプランをご提案いたします。
\全国120拠点以上の相談窓口/





